IIJでは、ローカル5Gの活用…
ローカル5G とは何か?
局所的な自営ネットワークとして多様な活用が期待されている「ローカル5G」。本稿ではローカル5Gの施策を中心に、その概要を解説する。
ローカル5Gの概要
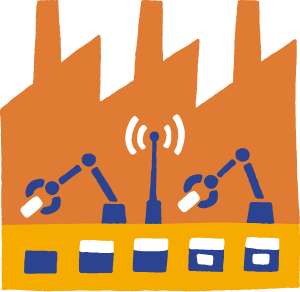
ローカル5Gとは、一般企業や自治体などが「限定された地域」において「自前」で構築・運用できる、第五世代移動通信ネットワーク(5G)の総称で、現在、総務省が制度設計を進めています。このように通信インフラ基盤を地域限定で整備する狙いはどこにあるのでしょうか?
最初に、これまでの移動通信ネットワークの変遷を簡単に振り返ると、1985年にアナログ通信(1G)として始まって以来、おおむね10年毎に進化を遂げ、国際標準にもとづいた4GとしてLTEが採用されたことで、音声通話だけでなく、データ通信も個人の携帯端末で行なえるようになり、人を中心にインターネットへ自由にアクセスする環境が整いました。
5Gでは、ミリ波を含む幅広い周波数帯に対応した5G NR(New Radio)と呼ばれる新たな無線通信技術により、さまざまなモノがつながる世界を目指しています。
5G NRでは、使用可能な周波数の帯域幅が格段に広くなるため、LTEの約10倍の超高速(eMBB:enhanced Mobile Broadband)や多数同時接続(mMTC:massive Machine Type Communication)が実現されます。加えて、LTEの約10分の1に短縮される応答速度による高信頼/低遅延(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency communication)も実現されるため、新たな無線フレーム構成を採用する点が鍵となります。
加入者情報の認証やデータ通信のポリシー制御などを担うコアネットワーク5GC(5G Core)は、無線アクセスとの組み合わせを考慮し、4G(LTE)と5GNRを併用するNSA型(Non-StandAlone)と、5Gを単独で実現するSA型(StandAlone)に大別されます。5Gのサービス開始当初は、4Gのコアネットワークを拡張したOption 3:NR(NSA型)となるため、eMBBのみが実現可能です。URLLCやmMTCは、Option 4:NR(SA型)が必要となり、2021年以降に実現する見通しです。
ローカル5Gの話に戻りますと、そもそも、なぜ5Gの周波数帯域の一部を、一般企業や自治体などに割り当てる必要があるのでしょうか?全国サービスの通信事業者(MNO)以外を対象とした理由は、5Gから利用される新たな周波数帯域の電波特性に答えが隠されています。
MNOに割り当てられている4Gの電波は、建物などの障害物があっても回折する「プラチナバンド」と呼ばれる700~900MHz帯(1GHz以下の周波数帯)を中心に構成されています。それに対し、2019年4月、MNO4社に割り当てられた5Gの帯域は、3.7/4.5GHz帯や28GHz帯といったより高い周波数帯です。
一般に、電波は周波数が高くなる(波長が短くなる)と直進性が増し、建物などの遮蔽物の影響を受けやすくなります。また、水蒸気や植生に遮断されやすく、空気中を伝搬する際の減衰幅が大きいため、電波が遠くまで飛びづらくなります。このため、特に周波数が高くMNOが使いづらい28GHz帯は、工場内でのロボット制御などから実用化が進むと考えられます。
ローカル5Gの狙い
ローカル5Gは、MNO以外を対象に、2019年12月頃から28GHz帯の免許申請が始まる予定です。おもな目的は人手不足や高齢化が顕著な地方の活性化で、例えば、無線LAN(Wi-Fi)の代用として、工場や大型商業施設での利用が期待されています(ローカル5Gは申請区域外に電波が漏れることを禁じていますが、28GHz帯は窓ガラスなどでも電波が遮蔽されるため、問題になることは少ないと見られています)。
なお、ローカル5Gでは、Sub-6GHzに含まれる28GHz帯より波長が長い4.5GHz帯の割り当ても検討されており、2020年後半に免許申請の受付が始まる見通しです。4.5GHz帯は、28GHz帯に比べて、エリアを面的に確保できます。隣接する区画との電波干渉の問題や既存の公共業務用システムとの調整が課題になりますが、順調に進めば、4.5GHz帯の実用化にも大きな期待が寄せられています。
(イラスト/高橋庸平)
※IIJグループ広報誌「IIJ.news vol.154」(2019年10月発行)より転載
気になることがあればお気軽に

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)